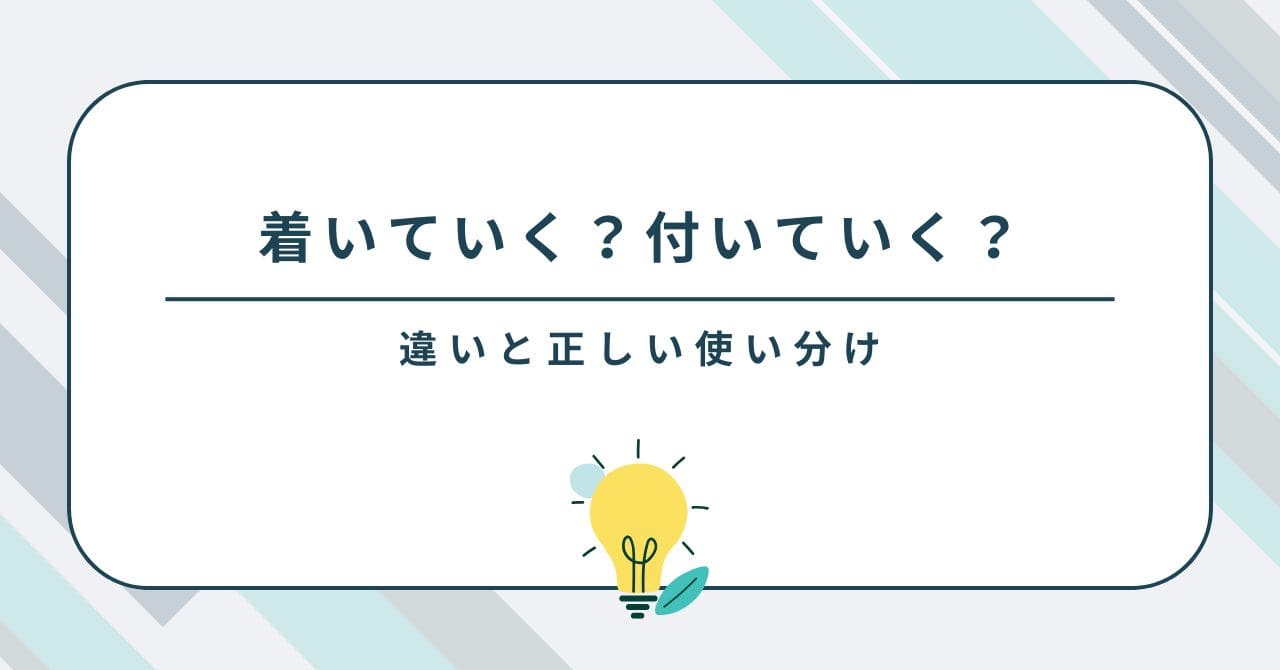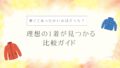「着いていく」と「付いていく」。どちらも読み方は同じ「ついていく」ですが、漢字が違うだけで意味が大きく変わることをご存じですか?
SNSやメール、ビジネス文書などでもよく使う言葉だからこそ、「どっちが正しいの?」と迷いやすいものですよね。
実際、辞書を見ても一言で断定されているわけではなく、文脈によって漢字を使い分ける必要があります。
結論からいうと—— 目的地やゴールに向かうときは「着いていく」/人や方針・流れに従うときは「付いていく」 が自然です。
ただし、現代の日本語では例外も多く、迷ったときは 「ひらがなで書く方がていねいで誤解を避けやすい」 場合もあります。
この記事では、初心者の方でもパッと判断できるように、
✔ 意味の違い
✔ 使用シーン別の例文
✔ ビジネスでの正しい表記
✔ 誤用例と避けたいポイント
✔ 迷ったときの判断チェック表
をやさしく、やわらかい雰囲気でまとめました。
読み終わるころには、「どっちの漢字にすればいいんだろう…」というモヤモヤがスッキリして、自信を持って「ついていく」を使いこなせるようになります。
- まず結論|違いは「ゴールに向かう」か「相手に従う」か
- 一目でわかる!「着いていく」と「付いていく」の比較表(意味・対象・使用シーン・例文)
- 「着いていく」の意味と正しい使い方
- 「付いていく」の意味と正しい使い方
- 間違えやすい!「着いていく」と「付いていく」のNG例と正しい表現
- 「付いていく」が使われがちな理由は?メディア・公用文での表記の傾向を解説
- ビジネスメールの「上司についていく」はどっち?
- LINE・SNS・チャットではどう使うと自然?
- 関連語・言い換え表現まとめ
- 辞書で調べても迷う理由|現代日本語の変化と文脈判断
- 【保存版】3秒で判断!「着いていく/付いていく」チェック表
- まとめ:もう迷わない「ついていく」——意味を知って正しく使いこなそう
まず結論|違いは「ゴールに向かう」か「相手に従う」か

まず最初に整理しておくと、「着いていく」と「付いていく」の違いはとてもシンプルです。
● 目的地・場所・ゴールに向かう → 着いていく
例:駅まで着いていく/会場まで着いていく
● 人や方針・考え・流れに従う → 付いていく
例:先輩の指導に付いていく/流行に付いていく
どちらも読み方は「ついていく」ですが、何に向かうのか、何を基準に動いているのかで漢字が変わります。
「ゴールがある行動」なのか、「相手や方針に合わせる行動」なのかを意識すると、スッと判断しやすくなります。
また、現代の日本語では文脈によって例外も多く、ビジネスメールやSNSでは誤解を避けるために「ひらがな表記」が使われることもあります。
どの表記が絶対に正解というものではなく、シーンや目的に合わせて選ぶのがいちばん自然で丁寧な使い方です。
一目でわかる!「着いていく」と「付いていく」の比較表(意味・対象・使用シーン・例文)

2つの言葉の違いをより直感的に理解できるように、表でまとめてみました。
同じ「ついていく」でも、漢字が変わるだけで伝わる印象や意味が大きく変わります。
| 項目 | 着いていく | 付いていく |
|---|---|---|
| 意味 | ゴール・目的地に向かう | 人や方針・流れに従う/遅れないよう努力する |
| 対象 | 場所・目的地・会場・駅 など | 人・考え・指導・流行・時代 など |
| ニュアンス | 行動の“到達点”がある | 関係性や“寄り添い”のイメージ |
| 使用シーン | 移動・案内・集合・同行 | ビジネス指導・教育・SNS・流行・自己成長 |
| 例文 | 「駅まで着いていくね」 | 「先輩のアドバイスに付いていく」 |
表にするとすぐに違いが見えてきますが、実際の文章では迷いやすいケースもあります。
特に、比喩表現を使った文章では判断に悩む場面が多いもの。
たとえば「時代についていく」「最新技術についていく」などは、目的地のある移動ではなく“遅れないように努力する”意味なので「付いていく」を使うのが自然です。
一方で、「駅まで」「会場まで」のように具体的な場所・目的地を示す言葉が入っている場合は、迷わず「着いていく」で大丈夫です。
まずは “場所なら着・相手なら付” を意識しておくと判断がとてもスムーズになります。
「着いていく」の意味と正しい使い方

「着いていく」は、目的地や到着点が明確に存在しているときに使う表現です。
誰かと一緒にどこかへ移動したり、目的地に向かって進むときに使われます。
漢字の「着」は“到着する”を表すため、ゴールのある行動と相性が良いのが特徴です。
目的地や到着が明確な状況で使うのが基本
たとえば、「駅まで着いていくね」「会場まで着いていく」「入口まで着いていくよ」など、具体的な場所が示されているときは必ず「着いていく」を使います。
行動の目的地がハッキリしているときに選ぶ漢字だと覚えておくと迷いにくくなります。
具体的な使用シーン(旅行/集合/案内/移動)
- 子どもの登校に付き添うときに「学校まで着いていく」
- 友だちと待ち合わせが不安だから「駅の南口まで着いていくよ」
- 初めて行くお店に案内するとき「入口まで着いていくから安心してね」
目的地に向かう、誰かを案内する、一緒に移動する——こうした状況ではすべて「着いていく」が自然な表現です。
誤用しやすいケース(比喩表現には使わないのが自然)
ただし、「未来についていく」「流れについていく」「技術についていく」などの“遅れないよう努力する”という比喩的な表現では「着いていく」は使いません。
このような抽象的な対象には、到達点がないため“付いていく”が正しい使い方になります。
場所や目的地と結びついているかどうかを意識してみると、「着いていく」を使うシーンが自然と判断できるようになります。
「付いていく」の意味と正しい使い方

「付いていく」は、人や考え・方針・流れに従うときに使う表現です。
漢字の「付」には“くっつく・より添う”という意味があるため、物理的な移動ではなく、相手に合わせたり遅れないよう努力するイメージが強いのが特徴です。
「一緒に成長する」「寄り添う」「サポートする」という温かいニュアンスも含まれています。
人・方針・考え・流れに従う場面で使う
たとえば、「先輩の指導に付いていく」「先生の方針に付いていく」「上司のビジョンに付いていく」といった場面ではすべて「付いていく」が自然です。
相手の思いややり方を尊重しながら寄り添っていく意味があり、人間関係の中で使われることが多い表現です。
抽象的な対象にも使えるのがポイント
「流行に付いていく」「時代に付いていく」「最新技術に付いていく」など、目に見えない対象にも使えるのが「付いていく」の大きな特徴です。
ここには“遅れないように努力する・歩調を合わせ続ける”ニュアンスが含まれており、現代のビジネスシーンやSNSでもよく見られる使い方です。
誤用しやすいケース(目的地には使わないのが自然)
「駅まで付いていく」「会場まで付いていく」と書いてしまうのは誤用です。
移動や到着を表す行動には「着いていく」を使うのが自然で、目的地がある表現とは相性が良くありません。
迷ったときは“場所なら着・相手なら付”を思い出すと判断がとてもスムーズになります。
「付いていく」は、努力・寄り添い・協力など、心の動きが大きく関係している優しい表現です。
人や考えに寄り添いながら成長していきたいときにぴったりの言葉だと言えます。
間違えやすい!「着いていく」と「付いていく」のNG例と正しい表現

2つの言葉は意味が異なるにもかかわらず、文章にすると混同しやすい場面がたくさんあります。
ここでは、よくある間違いと、どう書けば自然で丁寧に伝わるのかをやさしく整理していきます。
目的地なのに「付いていく」を使ってしまう場合
❌ 例:駅まで付いていくね/会場まで付いていくよ
→ これは目的地のある“移動”なので不自然な表現になります。
⬇ 正しい表現
✨ 例:駅まで着いていくね/会場まで着いていくよ
「着」は“到着する”という意味があるので、場所・目的地があるときは必ず「着いていく」を選びましょう。
従属なのに「着いていく」を使ってしまう場合
❌ 例:先輩の意見に着いていく/流行に着いていく
→ この場合は相手や流れに歩調を合わせる意味なので誤りです。
⬇ 正しい表現
✨ 例:先輩の意見に付いていく/流行に付いていく
「付」は“寄り添う・従う”という意味が含まれているため、人・思想・流れに合わせるときは「付いていく」を使うのが自然です。
迷ったときのシンプルな判断ポイント
どちらを使うか迷ったら、まずこの2つだけ思い出してください。
| 判断ポイント | 選ぶ漢字 |
|---|---|
| 行き先・場所・目的地がある | 着いていく |
| 人・方針・流れ・考えに合わせる | 付いていく |
| どうしても迷う/誤解を避けたい | ひらがな「ついていく」 |
どちらの表記も間違いではありませんが、大切なのは“相手に正しく伝わるかどうか”。
迷ったときはひらがなにすることで角が立たず、文章全体がやわらかくなります。
「付いていく」が使われがちな理由は?メディア・公用文での表記の傾向を解説

ここまで「着いていく」と「付いていく」の違いを整理してきましたが、実は新聞・テレビ・広報文などの“公的な文章”では「付いていく」を採用するケースが多いと言われています。
これは、必ずしも「付いていくのほうが正しい」という意味ではなく、幅広い文脈に対応しやすく誤解が生まれにくいという理由から採用されやすいのです。
たとえば、NHK放送文化研究所や新聞社では、“目的地の移動”であっても文脈によっては誤解を避けるために「ひらがな」「付いていく」を使う判断が取られることがあります。
多くの読み手がいる文章では、漢字の意味にこだわりすぎて意図と異なる受け取り方をされるのを避けたい、という配慮が背景にあります。
また、ビジネスメールでも「同行なのか従属なのか」が文脈だけでは判断しにくい場合があり、その際にひらがな表記の「ついていく」が無難で丁寧とされることも増えています。
つまり、
- 漢字の違いを意識して使い分けるのが基本
- でも状況によっては「ひらがな」で柔らかくするのも安心
というスタンスが、現代の日本語では自然だと言えます。
ビジネスメールの「上司についていく」はどっち?

仕事の場面でいちばん迷いやすいのが「上司についていく」という表現です。
出張や取引先訪問などの“同行”なのか、指導や方針に“従う”ことなのかで使う漢字が変わり、どちらを書けばよいのか悩んでしまう人がとても多い言葉でもあります。
ここでは、状況別にやさしく使い分けを整理していきます。
ケース1:物理的な移動で同行する →「着いていく」
上司と一緒に移動する、同行するといった“目的地がある行動”の場合は「着いていく」が自然です。
✨ 例文
「明日の出張は課長と大阪支店まで着いていきます。」
「訪問先の会社まで部長と着いていきます。」
“どこへ行くのか”という到達点があるときは、迷わず「着いていく」で大丈夫です。
ケース2:指導や方針に従う →「付いていく」
上司の考え方や指導、方向性に共感し、歩調を合わせていく意味の場合は「付いていく」を使います。
✨ 例文
「今後も部長のご指導に付いていきたいと思っています。」
「課の方針に付いていき、チームとして成長したいです。」
目に見えない“方針・考え”が対象となっている点がポイントです。
迷ったときは「ひらがな」が丁寧で安心
ビジネスメールでは、漢字を誤って使ってしまうと意図と違う印象を与えてしまう場合があります。
どうしても判断に迷う・誤解を避けたい・柔らかく伝えたい、そんなときは ひらがなの「ついていく」 がいちばん無難で丁寧です。
✨ 例文
「今後もついていきたいと思っています。」
「引き続きついていかせていただきます。」
ビジネスの文章では“伝わりやすさと安心感”がとても大切。
漢字にこだわりすぎず、状況に合わせて使い分けることで、相手に丁寧でやわらかい印象を与えることができます。
LINE・SNS・チャットではどう使うと自然?
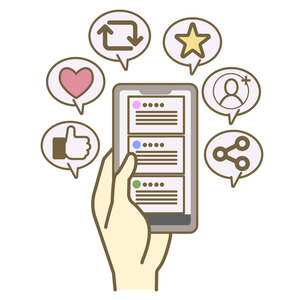
ビジネスメールと違って、LINEやSNS、チャットではそこまで漢字にこだわらなくても大丈夫です。
文字をパッと見てすぐ理解できるか、読み手に負担がないかがとても大切なので、少しでも堅く感じられる漢字より ひらがなの「ついていく」 が自然でやわらかく、好印象になることが多いです。
メッセージでは読み手の負担を減らすのがポイント
チャットは文章量が少なく短いからこそ、漢字が多いと少し堅い印象になりがち。
特に「着いていく」「付いていく」は字面がしっかりしているため、カジュアルな会話ではひらがなで柔らかく見せたほうが伝わりやすいことが多いです。
ひらがなが柔らかく伝わりやすい理由
- 親しみが出る
- 相手に距離を感じさせない
- 誤解を生みにくい
この3つの理由から、日常会話やSNSでは「ついていく」を選ぶ方が丁寧でやさしい印象になります。
シーン別の自然な例文
💬 友だちとの会話
「映画館ついていくよ〜!」
「ライブ、私もついていく!」
🏠 家族とのやりとり
「スーパーまでついていくね」
「帰りに図書館よるならついていく〜」
💼 ビジネスチャット(やわらかくしたいとき)
「次のミーティング、私もついていきます!」
「資料作成の方針、私もついていきますね」
仕事の場では気をつかうことが多いぶん、チャットでやわらかく伝えたい場面はたくさんありますよね。
そんなとき、敢えてのひらがな表記はやさしさと安心感が出せる便利な選択肢です。
関連語・言い換え表現まとめ

「着いていく」「付いていく」は便利な言葉ですが、文章の雰囲気やニュアンスによっては別の表現を使ったほうが自然な場合もあります。
ここでは、シーン別に使いやすい関連語・言い換え表現をまとめました。
語彙の引き出しが増えると、メールやチャットの文章もグッと洗練されます。
行動を表すときに使える言い換え(移動・同行系)
- 同行する
- 一緒に行く
- 案内する/案内していく
- ついて回る(カジュアル)
✨ 例文
「明日の会議は部長に同行します。」
「駅まで一緒に行くよ!」
「着いていく」の代わりとして、丁寧さや落ち着いた印象を与えたいときに便利です。
人・考え・方針に寄り添うニュアンスの言い換え
- 付き従う(かたい印象)
- 寄り添う(柔らかい印象)
- 伴走する(ビジネスで人気のワード)
- サポートする
- フォローする
✨ 例文
「課のビジョンに伴走していきたいです。」
「新人さんの挑戦に寄り添っていきたいと思っています。」
「付いていく」の代わりに使うことで、協力・支援・前向きさがより丁寧に伝わる表現になります。
ビジネスで使うと印象がよくなる便利ワード
| ニュアンス | 言い換えの提案 |
|---|---|
| 一緒に進めたい | ご一緒できれば嬉しいです/並走させてください |
| 方針に従いたい | 方針に沿って進めます/方向性を共有して取り組みます |
| サポートしたい | 必要あれば伴走・支援します |
強い従属の印象を避けつつ、前向きな姿勢を伝えたいときに使える表現です。
とくに仕事では「従います」よりも「伴走します・沿って進めます」のほうが柔らかく丁寧に聞こえることが多いです。
言い換え表現を知っておくと、文章の雰囲気をやさしく整えながら相手に気持ちよく伝えられるので、ビジネスでも日常でもとても役立ちます。
辞書で調べても迷う理由|現代日本語の変化と文脈判断

「着いていく」と「付いていく」を辞書で調べても、「どちらが正しいのかは文脈による」と書かれていることが多く、スッキリしない…と感じた経験のある方も多いのではないでしょうか。
これは、どちらか一方だけが正解というより、言葉が使われる状況によって最適な漢字が変わるためです。
昔の日本語は、単語の意味によって明確に漢字を使い分ける傾向が強かったのですが、現代の日本語は「文脈を優先して判断する」方向へ変化しています。
そのため、辞書でも断定せず「こういうときはこの表記が自然」「ただし例外もある」という形で説明されることが多いのです。
つまり、迷ってしまうのは間違いではなく、とても自然なこと。
むしろ、どの場面でどちらを選べば相手に伝わりやすいかを考えられるほうが、現代では“言葉が丁寧に使える人”と言えます。
漢字の正しさだけにこだわらず、状況や読み手のことを思いやって表記を選ぶ——その姿勢こそが、これからの日本語ではいちばん大切なのかもしれません。
【保存版】3秒で判断!「着いていく/付いていく」チェック表
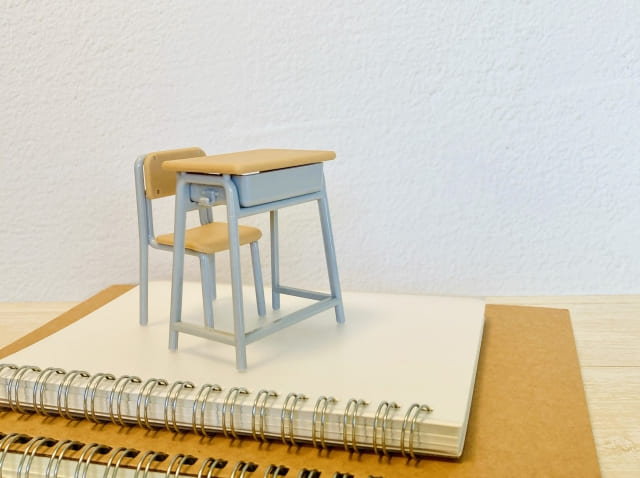
ここまで読んで「だいぶ分かってきたけれど、文章を書いていると迷ってしまう場面がありそう…」という方のために、パッと判断できるチェック表を用意しました。
深く考えなくても直感的に選べるようになっているので、困ったときに思い出すだけで安心できます。
チェックポイント一覧
| 判断の視点 | 当てはまる状況 | 選ぶ表記 |
|---|---|---|
| 目的地・場所がある | 駅・会場・店・入口 などに向かう | 着いていく |
| 人・考え・流れに合わせる | 上司・指導・流行・時代 など | 付いていく |
| どちらとも取れる/誤解を避けたい | メール・SNS・チャット | ついていく(ひらがな) |
もっとシンプルに覚えたい場合は…
場所 → 着いていく/人・流れ → 付いていく
この2つだけ思い出せばほとんどの場面で迷いません✨
今日からすぐ使えるワンフレーズ
- 迷ったら、ひらがなにすると優しく・丁寧・安全💐
- 相手や場面への“気づかい”が伝わる表記がいちばん素敵です
たとえ迷っても大丈夫。
どの表記を選ぶか考えられるというだけで、あなたの文章はすでに丁寧で思いやりのあるものになっています。
自信を持って「ついていく」を使っていきましょう。
まとめ:もう迷わない「ついていく」——意味を知って正しく使いこなそう
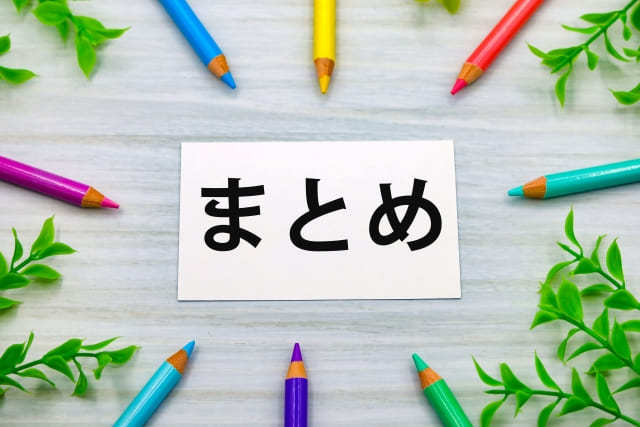
「着いていく」と「付いていく」は、どちらも読み方は同じでも、込められた意味やニュアンスは大きく異なります。
● 目的地・場所に向かう → 着いていく
● 人・指導・考え・流れに従う → 付いていく
まずはこの2つだけ覚えておけば、ほとんどの場面で迷わず表記を選べます。
そして、迷ったときや相手に柔らかく伝えたいときは、ひらがなの 「ついていく」 にすることで丁寧さも誤解回避も叶います🌼
ビジネス、日常会話、SNS、どの場面でも大切なのは“正しさ”よりも“伝わりやすさ”と“思いやり”。
表記の使い分けができるようになると、文章にも気遣いがにじみ、相手に好印象を与えることができます。
この記事が、これから言葉を使うたびに自信につながる小さな味方になれたら嬉しいです。
今日からあなたの文章がもっとやさしく、もっと素敵に伝わりますように。